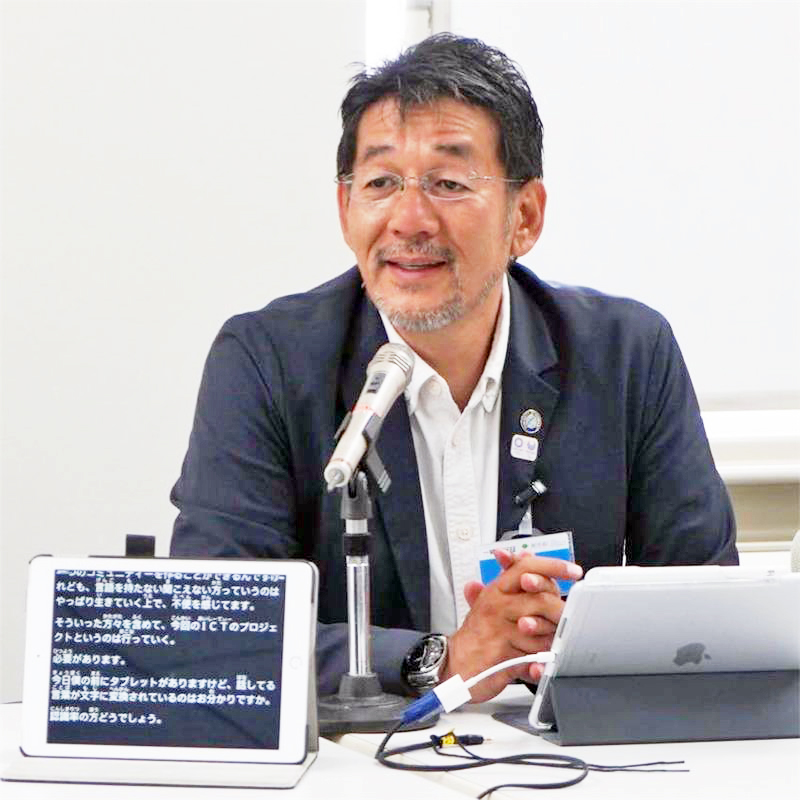プログラム
- S-48
- セッション
避難所でどう伝える? ICTと遠隔手話通訳の実践 ー自治体でできる、ろう者・難聴者への情報提供 最前線ー
主催団体:
株式会社プラスヴォイス
協力団体:
新潟県加茂市、新潟県聴覚障害者協会、
石川県聴覚障害者災害救援対策本部、国立大学法人群馬大学
-
- 14:30~16:00
-
1F 展示控室4A
- 自治体向け
- 一般向け
-
避難・避難所
-
防災行政
災害時、音声情報が届かないろう者・難聴者にとって、命を守る情報提供は不可欠です。2025年施行の手話施策推進法や災害対策基本法改正により、自治体には情報提供体制の整備が求められます。セッションでは、能登半島地震で実際に活用されたICTを使った遠隔手話通訳の活用事例を紹介し、通訳者も被災する中でどう支援を継続するか、地域・自治体・専門家の連携による「誰ひとり取り残さない防災」の実現方法を共に考えます。
- 現地出展+オンライン同時配信・後日アーカイブ配信


団体プロフィール
-
主催団体名株式会社プラスヴォイス
-
WEB
-
SNS