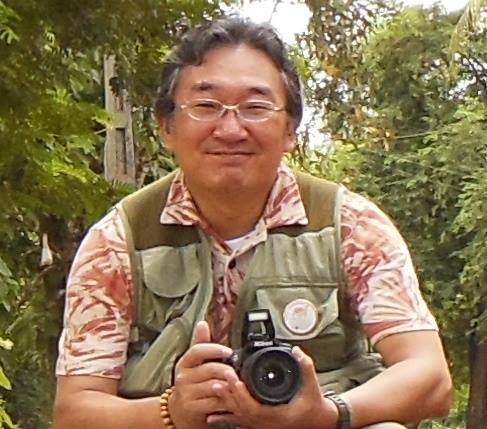プログラム
- S-43
- セッション
福祉避難所としての特別支援学校の可能性と課題
主催団体:
特別支援学校の災害対策を考えるfacebookグループ
協力団体:
常葉大学社会環境学部小村研究室/兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科青田研究室/大阪府立支援学校PTA協議会OB会/静岡県立富士特別支援学校/海ぼうずの会(「ふじのくにDIGセミナー」参加者の会)
-
- 10:30~12:00
-
1F 展示控室1
- 自治体向け
- 一般向け
-
避難・避難所
-
インクルーシブ
2024年秋、内閣府から全国の防災行政・教育関係者へ「特別支援学校を障害のある子供のための福祉避難所に指定する取組の推進について」との通知がありました。通い慣れた特別支援学校が、そこに通う児童生徒や卒業生とその家族の福祉避難所になることは、基本的には歓迎すべきと思います。ただ、この通知を生きたものにするには、課題の整理とさらなる工夫が必要ではないでしょうか。一緒に考えてみませんか。
- 現地出展+オンライン同時配信・後日アーカイブ配信

紹介動画
紹介動画
https://www.youtube.com/@jo2uym
※外部サイトに移動します

団体プロフィール
-
主催団体名特別支援学校の災害対策を考えるfacebookグループ
-
WEB